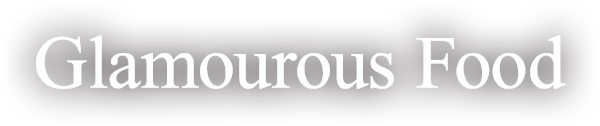【イタリアワインの格付け】
こんにちは!
皆さん、イタリアワインって分かりにくいですか?
いわゆるニューワールド(おおむねヨーロッパ以外ですね♪)のワ
フランスはボルドー、ブルゴーニュなど産地に対してしっかりと格
さて、ここにきてイタリア、はっきり言って分かりにくいんです。
理由はいろいろありますが、イタリア人の個人主義、ローカル主義
要するに、「俺の地元が最高!」ってみんなが思ってるのではない
それはそれでいいことですけどね^^
・イタリアワインの格付け
イタリアワインは大きく分類すると、VINO、IGP、DOPの
まず、VINOヴィーノですが、ある意味これが一番わかりやすい
端的に言えば、なにも規制のないテーブルワインです。
例えば、南のプーリア州で作ったブドウと北のピエモンテ州で作っ
去年収穫のブドウと今年収穫のブドウを混ぜてもいいんです。
反面、高級ワインにはなりません。
小売価格で言っても1,000円以下のものがほとんどでしょう。
次に、IGPですが、そもそもEUではこれをIGPと呼ぼう!と
どちらかといえば7対3くらいでIGTが多いのではないかと思い
で、IGTとは何かと言われますと、難しくいえば「保護地理表示
「Terre Siciliane IGT」と書かれていれば、「このワインはシチリア産のブドウで
そして、DOPです。
DOPもIGPと同じく、DOC、DOCGの表示も認められてい
しかもDOPとDOC、DOCGは併記も認められているのです。
つまり「キアンティDOP」「キアンティDOCG」「キアンティ
なお、DOCとは「統制原産地呼称」、DOCGは「保証つき統制
ですので、VINO、IGT、DOC、DOCGの順に格付けは上
・結局どれが上なんだ?!
正直、ここまでならそんなに難しいことはないんです。
問題はここからです。
例えば、フランスならDOPに相当する、AOCという法律があり
しかもそれが広域エリア名、狭域エリア名、村名、畑名とゆるぎな
ブルゴーニュであれば、「ブルゴーニュ」「コートドニュイ」「ヴ
それが「ジュヴレシャンベルタン」でも「シャンボールミュズィニ
さてイタリアではどうかと言いますと、格付けが一番上のDOCG
その歴史は古く、1716年にはこれを保護してまがい物から守ろ
ですがその後「キアンティ」はエリアをどんどん拡大していくので
その結果、近年になって本来の「キアンティ」であったエリアは「
これがイタリアワインは難しいと思われる原因のひとつですね。
コンビニで1,000円以下で売っている「キアンティ」と
造り手によっては1万円を越える「キアンティ クラッシコ」が
同じ最上位の格付けDOCGに認定されているんです。
この辺りで、結局どっちが上なんだ?!となるのですが、さらに、
・スーパータスカンの登場
さらにイタリアワインのややこしいことに、1970年代から品質
従来、大樽で長期熟成が必要だったバローロの改革をした「バロー
また、「キアンティクラッシコ」地域の生産者たちも、規制にとら
これが近代的なスタイルで消費者に受け入れられ、「スーパータス
規制にとらわれない自由な発想、ということは要するにDOC、D
つまり、格付けで言えば、IGT、またはvino(かつてはVd
そんなこんなで、イタリアにおいては
2~3万円で格付けは一番下のvino
1000円で格付けは一番上のDOCG
ということもあるのです。
・そうでないのも中には…
あることはあるんです。
DOC「ロッソ・ディ・モンタルチーノ」
DOC「ロッソ・ディ・モンテプルチアーノ」とDOCG「
ただ、DOC「ロッソ・コーネロ」の上位にDOCG「コーネロ」
・ならばどのようにイタリアワインを覚えるか
これは個人的な見解で少し乱暴な言い方ですが、
まずはニューワールドと同じように、品種を覚える。
サンジョヴェーゼ、ネッビオーロ、アリアニコ、
そんな時は写真に撮ってしまえばいいんです^^
レストランで、あるいはワインショップで、
そして、「前に飲んだこれがおいしかったんだけど、
そうしたらそこはプロですから、
また、そのために我々ソムリエがいるのだと、私は思っています。
何度かそんなやりとりがあれば、
難しい格付けのことは一旦おいといて、